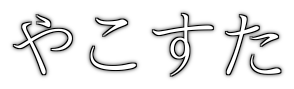こんにちは!やこです。今回は数学検定の概要や各級のレベルや対策方法、そして申し込み方法などを解説していこうと思います。
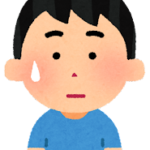
数検に申し込みをしたいんですけど、どの級を受ければいいのかわからないし、対策法や申し込み方法もわかりません!
以上のような悩みをこの記事で解決していきます。
- 数学検定の概要
- 数学検定を合格するには?
- 数学検定の申し込み方法
数学検定は級も多く、申請方法なども少しややこしいですが数学のスキルを証明するのに役に立つ資格なので是非取得しておきましょう!
実際に著者自身も数学検定を受験し、合格しているので(2級)この記事を参考にしていただけると幸いです。
数学検定を合格し、数学スキルを身につけていきましょう!
数学検定の概要
数学検定とは?
数学検定とは正式名称実用数学機能検定と呼ばれている公務財団日本数学検定協会が実施している数学の検定です。
一般的に数検と呼ばれています。
自分の数学の実力を確かめられる日本でも有名な数学の試験です。
数検の公式ホームページはこちらから↓
数学検定・算数検定(実用数学技能検定) | 公益財団法人 日本数学検定協会 (su-gaku.net)
数学検定の階級は?
数学検定には階級があり、各級によって難易度が変わってきます。
こちらは数学検定の階級一覧とそのレベルです。
| 階級 | レベル目安 |
| 1級 | 大学生・社会人レベル |
| 準1級 | 高校3年レベル |
| 2級 | 高校2年レベル |
| 準2級 | 高校1年レベル |
| 3級 | 中学3年レベル |
| 4級 | 中学2年レベル |
| 5級 | 中学1年レベル |
このように数検にはさまざまな階級があり、自分のレベルに合わせた級を受けることができます。

中学生なら3級、高校生なら準1級を目指して勉強してみよう!
数学検定の各階級の合格率は?
数学検定の合格率はどの検定でも同じではあると思いますが、基本的に階級が上がるごとに難易度が上がってくるので合格率が下がっていきます。
こちらは数学検定の各階級の合格率のデータです。(2020年の合格率)
| 階級 | 合格率 |
| 1級 | 12.1% |
| 準1級 | 22.5% |
| 2級 | 34.5% |
| 準2級 | 44.5% |
| 3級 | 66.6% |
| 4級 | 73.4% |
| 5級 | 77.1% |
このように級が上がるごとに合格率は下がっていきます。中でも一級は合格率がたったの12.1%しかなく、とても合格するのが難しいというのが分かります。
レベルの目安だけでなく、合格率なども考慮して自分のレベルに合った級の受験を検討してみるのもよいと思います。
数学検定を合格するには?
数検の対策 3つのポイント
自分の受けたい級を決めたら、次は実際に合格するために対策勉強をしていきます。
でも数学検定をどのように勉強したらいいかわからない人も多いはずです。
ですので今回は数学検定を合格するための方法を伝授したいと思います。
数学検定を合格するには3つのポイントがあります。
- 1 数検の問題形式と自分の受ける級の出題範囲を知る
- 2 自分の受ける級の出題範囲を把握して勉強する
- 3 過去問などで問題の傾向を把握しておく
ではこれらの3つのポイントを順番に詳しく解説していきます。
point1 数検の問題形式を知る
まずは数検の問題形式を知りましょう。数学のテストには問題の答えを書くだけのものやすべて白紙から記述させるものもあります。では数検はいったいどのような問題形式なのかというと、
数学検定はどの級も記述式問題が出題されます。
「どの級でも記述式問題が出される」ということは、どの級を受ける人でも記述式問題の対策は必須となります。
なので普段の学習で記述式の問題をあまり解く機会がない方などは是非数検の対策の一環として記述問題を一度問題集などで解いてみてはいかがでしょうか。
point 2 自分の受ける級の出題範囲を把握して勉強する
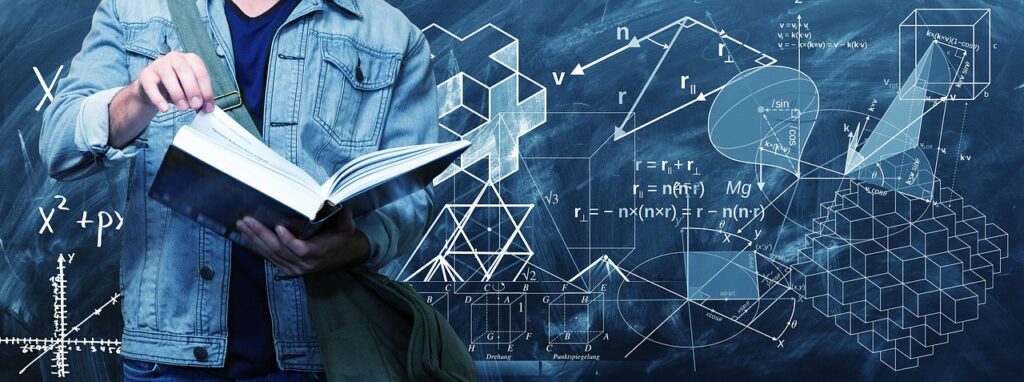
数検の問題形式を理解したら次に自分の受ける級の出題範囲を把握しておきましょう。
例えば、数検3級を受けるとしたら数検3級は中3レベルなので中3の数学の範囲が主に出題されます。中3数学で学ぶ内容は次の通りです。
- 因数分解や平方根
- 二次方程式、二次関数
- 相似や三平方の定理
これらの内容をしっかりと勉強すれば数検3級の対策はバッチリと言えるでしょう。
同様に他の級でも出題範囲の内容をしっかりと対策すれば、合格を狙えるでしょう。
point 3 過去問などで問題の傾向を把握しておく

出題範囲の勉強を完了したら最後にやるべきなのは、やはり数検の問題の傾向を知ることです。
数検は毎回同じ級でも出題される分野は異なっています。ですが毎年異なるとはいえやはり出題されやすい分野と出題されにくい分野があります。

例えば、数検2級や準1級だと微分、積分分野が毎回頻出だよ!
ですので問題の傾向を掴んでおくのが重要となります。
そして問題の傾向を掴むのに最適な手段は当然ながら数検の過去問となります。
過去問をやっておくことで、次のメリットがあげられます。
- 試験に慣れる練習になる
- 問題の傾向がつかめる
- 問題の難易度がわかる
このように過去問をやることで多くのメリットが得られますのでぜひ過去問一度解いてみてはいかがでしょうか。
過去問を試してみたい方は、こちらの公式ホームページから過去問をダウンロードしてください(一回分しかありませんので、何回分か解きたい方は過去問題集を活用してください!!)。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
検定過去問題 | 数学検定・算数検定(実用数学技能検定) (su-gaku.net)
数学検定の申し込み方法は?

それでは実際の数検の申し込み方法を解説していきます。
ただ申し込みを行う前に自分の受ける級の検定料を確認しておいてください。数検は級によって検定料が違います。
| 受験方法 | 1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 個人受検 | 8500円 | 7300円 | 6500円 | 5600円 | 4900円 | 4300円 | 4300円 |
| 提携会場受検 | 実施なし | 7300円 | 6500円 | 5600円 | 4900円 | 4300円 | 4300円 |
| 団体受検 | 実施なし | 6400円 | 5600円 | 4800円 | 4300円 | 3800円 | 3800円 |
なお、注意点として1級の提携会場受検と団体受検は実施されていません。

個人受検と提携会場受検はどの級も値段が同じだけど、団体受検は他の二つの受検法と比べて検定料がどの級も安いよね!
また上の表を見た通り、申し込みの種類は次の3通りがあります。
- 個人受検
- 提携会場受検
- 団体受検
では一つずつ申し込み方法を解説していきます。
個人受検の申請の手順
個人受検とは、年3回実施され、協会が全国主要都市に設けた個人受検会場で受検する方法です。
では個人受検の申請方法の手順を解説していきます。申し込みページからこの記事の手順に沿って申し込みを進めてみてください。
数検公式の申し込みページはこちらから↓
お申し込み | 数学検定・算数検定(実用数学技能検定) (su-gaku.net)
1 日程を決める
まずは日程を決めてもらいます。数検の個人受検は年3回開かれ、4月、7月、10月にあるイメージが多いです。また会場は全国の主要都市(名古屋、大阪、東京、その他政令指定都市など)で開催されているのですが、個人受検では自分で会場を選択することができません。
ですので個人受検で開催される会場が自分の住んでる場所の近くにあるか確認しておく必要があります。(公式ページから確認できます。)
2 申し込み方法を選択する
個人受検では次の4通りの申し込み方法があります。
- 1 ネット申し込み
- 2 LINE申し込み
- 3 コンビニ申し込み
- 4 郵送申し込み
ネット申し込みは「CBT個人受験申込サイト」から申し込みをして検定料を払えば完了です。
LINE申し込みはLINEから公式アカウント「数検」を見つければそこから申し込みを行い、検定料を払えば完了です。
コンビニや郵送申し込みに関しては実際にコンビニや郵便局に出向いての申し込みとなります。
なお、一番のお勧めは間違いなくネット申し込みです。ネット申し込みが一番早く、楽に申し込むことができます。支払いはクレジットカードやコンビニ支払いも対応しているので困ることもないと思います。
3 申し込みが完了したら受検証が届くのを待つ
申し込みが完了したら、当日の時間割や持ち物、注意事項が記載されている「受検証」が指定した届くはずです。受検証が届けば後は、検定日当日に検定を受検するのみとなります。
提携会場受検の申請の手順
提携会場受検は年に複数回(個人受検よりも圧倒的に回数が多い)開催される検定日の中から希望する検定日と提携会場を選択して受験する方法です。早速申し込みの手順を解説していきます。
1 日程や会場を決める
提携会場受検は個人受検と違い、会場を選ぶことができます。そして会場を決めると同時に日程も決めます。
2 申し込みをする
個人受検では4種類の申し込み方法がありましたが、提携会場受検ではネット申し込みしかできません。なので提携会場受検で申し込みをしたい方は「CBT個人受験申込サイト」から申し込みを行います。
3 申し込みが完了したら受検証が届くのを待つ
申し込みが完了したら、当日の時間割や持ち物、注意事項が記載されている「受検証」が指定した届くはずです。受検証が届けば後は、検定日当日に検定を受検するのみとなります。
団体受検の申請方法
団体受検とは学校や学習塾などで実施され、団体が選択した検定日に行われます。
団体受検志願者の方は団体の担当者に申し込みます。なので学校の先生や塾の先生などに手続きをしてもらってください。
まとめ
この記事では数検の概要や各階級のレベル、申し込み方法について解説しました。
数検は級の種類も多く、申請方法も多いのでややこしいと感じるかもしれません。
しかし数検を取得しておくと、数学力の向上にもなるし一定の数学のスキルを持っているという証明にも役立ちます。

自分の数学のスキルを確かめたい方はぜひ数検を受検してみよう!