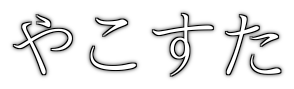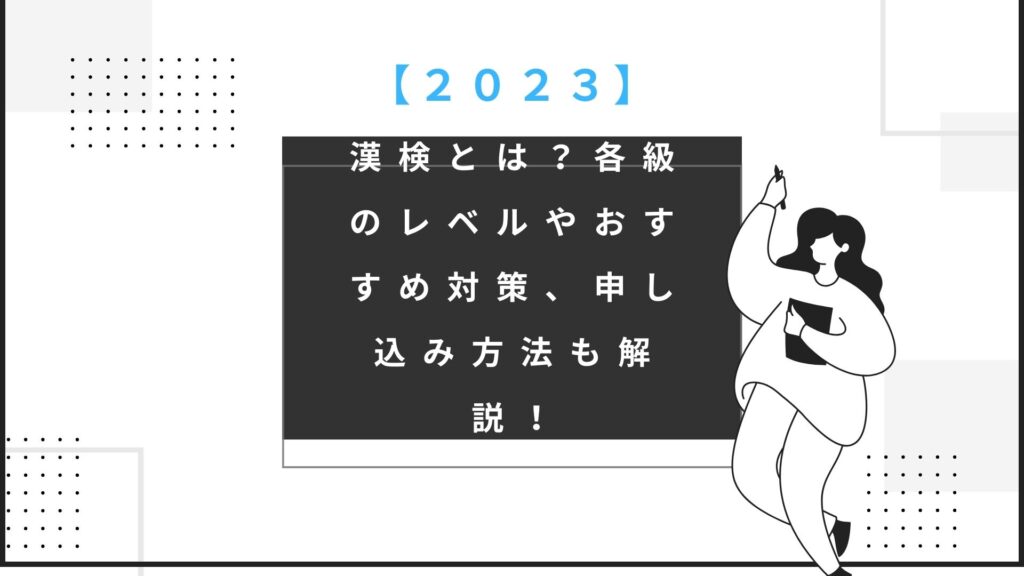
こんにちは!やこです。今回は漢字検定の概要や各級のレベルや対策方法、そして申し込み方法などを解説していこうと思います。
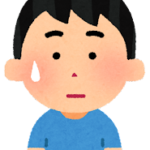
漢字検定に申し込みをしたいんですけど、どの級を受ければいいのかわからないし、対策法や申し込み方法もわかりません!
以上のような悩みをこの記事で解決していきます。
- 漢字検定の概要
- 漢字検定を合格するには?
- 漢検の申し込み方法
- まとめ
漢字検定は級も多く、申請方法なども少しややこしいですが漢字のスキルを証明するのに役に立つ資格なので是非取得しておきましょう!
実際に著者自身も漢字検定を受験し、合格(中学生の時3級取得)しているので、この記事を参考にしていただけると幸いです。
漢字検定を合格し、漢字スキルを身につけていきましょう!
漢字検定の概要
漢字検定とは
漢字検定(正式名称:日本漢字能力検定)とは、公務財団法人日本漢字能力検定協会が実施している漢字の読み書きなどの能力を計る検定であり、国内最大規模の漢字の試験でもあります。
日本漢字能力検定は略称として、漢検とよばれています。
公務財団法人日本漢字能力検定協会(漢検公式)のホームページはこちらから
↓↓↓
公益財団法人 日本漢字能力検定協会 (kanken.or.jp)
漢字検定の階級は?
漢検には多くの階級があり、各級によって難易度が変わってきます。
こちらは漢字検定の階級一覧とそのレベルです。(対象漢字数とは出題範囲とされる漢字の文字数です。)
| 級 | レベル | 対象漢字数 |
|---|---|---|
| 1級 | 大学・一般レベル | 約6000字 |
| 準1級 | 大学・一般レベル | 約3000字 |
| 2級 | 高校卒業レベル | 約2136字 |
| 準2級 | 高校在学レベル | 約1951字 |
| 3級 | 中学卒業レベル | 約1623字 |
| 4級 | 中学在学レベル | 約1339字 |
| 5級 | 小6レベル | 約1026字 |
| 6級 | 小5レベル | 約835字 |
| 7級 | 小4レベル | 約642字 |
| 8級 | 小3レベル | 約440字 |
| 9級 | 小2レベル | 約240字 |
| 10級 | 小1レベル | 約80字 |
このように漢検にはさまざまな階級があり、自分のレベルに合わせた級を受けることができます。

級の数がかなり多いので、小学生から大人まで幅広い世代の人が受検しているよ!
漢字検定の各階級の合格率は?
漢字検定の合格率はどの検定でも同じではあると思いますが、基本的に階級が上がるごとに難易度が上がってくるので合格率が下がっていきます。
こちらは漢字検定の各階級の合格率のデータです。(2022年度第3回の合格率)
| 級 | 合格率 |
|---|---|
| 1級 | 13% |
| 準1級 | 11.1% |
| 2級 | 28.9% |
| 準2級 | 38.5% |
| 3級 | 47.5% |
| 4級 | 53.2% |
| 5級 | 74.8% |
| 6級 | 79.3% |
| 7級 | 86.2% |
| 8級 | 82.3% |
| 9級 | 90.9% |
| 10級 | 94.9% |
このように級が上がるごとに合格率は基本的に下がっていきます(下の方の階級だと合格率が逆転することがある。(今回の場合:7級と8級))。1級は合格率がたったの13%しかなく、とても合格するのが難しいというのが分かります。
レベルの目安だけでなく、合格率なども考慮して自分のレベルに合った級の受験を検討してみるのもよいと思います。
漢字検定を合格するには?
漢字検定を合格する2つのポイント
自分の受けたい級を決めたら、次は実際に合格するために対策勉強をしていきます。
でも漢字検定をどのように勉強したらいいかわからない人も多いはずです。
ですので今回は漢字検定を合格するための方法を伝授したいと思います。
漢字検定を合格するには2つのポイントがあります。
- 1 漢検の問題形式と自分の受ける級の出題範囲を知る
- 2 漢検過去問で万全の試験対策をする
ではこれらの2つのポイントを順番に詳しく解説していきます。
ポイント1 漢検の問題形式と自分の受ける級の出題範囲を知る
漢検では、様々な種類の問題が出題されています。基本的な漢字の読み書きに加えて、対義語・類義語、同音・同訓漢字、四字熟語など問題の種類は多岐にわたります。
そんな漢検の出題形式は
記述式と選択式のどちらもあります。
漢字を実際に書かせる記述式とア~ウなどの選択肢から選ばせる選択式のどちらも漢検にはあります。どちらかと言えば漢字を書かせる記述式の問題の方が多い印象があるので、漢字の書きの練習をしっかりと練習しておく必要があります。
次に、自分の受ける級はどのくらいのレベルなのかを調べましょう。自分が受ける級のレベルを知ることで漢字はどのくらい覚えればいいのか、どのような対義語・類義語、四字熟語を覚えればいいのかおのずと見えてきます。
例えば3級(中学卒業レベル)を受けるとするならば、対策としては中学卒業までに習う漢字を一通り学習すればいいことになりますよね!具体的には中学で習う漢字一覧が乗っている参考書を買っておぼえていくといいでしょう。

このように自分の受ける級のレベルを知って、その級を受かるためにはどのような勉強をする必要があるのかを把握しておくとより合格に近づけるよ!
ポイント2 漢検過去問で万全の試験対策をする
過去問題集が漢検対策の参考書で一番おすすめな理由
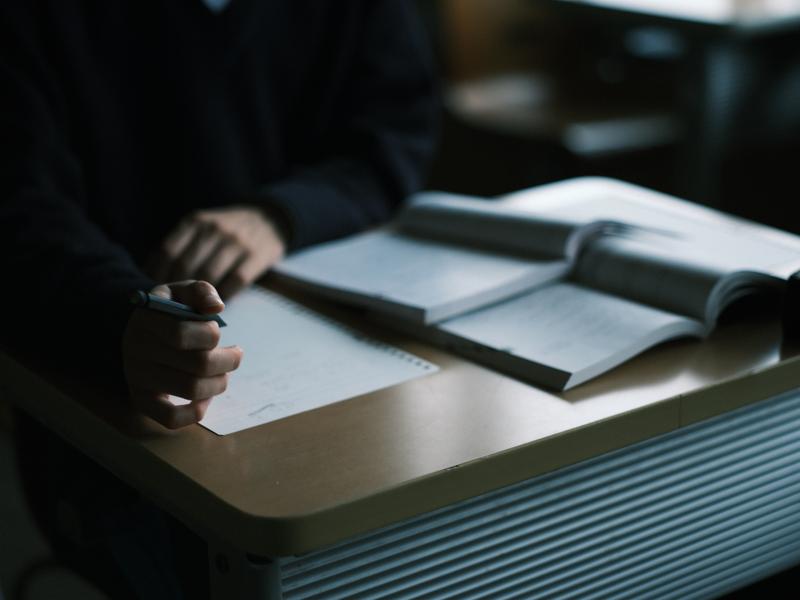
ポイント1では、自分の級においてどのような勉強をすればいいのか(勉強法)を知る重要性について話しました。ポイント2では、実際にポイント1で理解した勉強法を実際に試していきます。
漢検の対策で一番お勧めの参考書は間違いなく「漢検の過去問題集」です。
過去問題集では、実際に過去に出題された問題を解くことができるので様々なメリットがあるのです。
そのメリットは以下の通りです。
- 自分の級の漢字レベルがわかる
- 問題形式に慣れることができる
まず実際に過去問をやることで「自分が受検する級の漢字レベル」を知ることができます。どの程度のレベルの漢字が出題されているかを実際に問題を解くことで把握することができます。自分が受検する級の漢字のレベルを知ることができれば、後は自分が受ける級と同レベルの漢字を覚えていけばいいだけです。
また、漢検の問題形式に慣れることができるのも大きなメリットの1つです。漢検には様々な種類の問題が出題されています。過去問をいくつか経験しておくことで、いざ試験本番になった時に焦る可能性が非常に減ります。

見たことない問題の形式に出くわすと必要以上に焦ってしまう可能性があるから、あらかじめ過去問をやっておくことで見たことない問題をなくして、本番で焦らないようにするんだ!
漢検の申し込み方法

それでは実際の漢検の申し込み方法を解説していきます。
ただ申し込みを行う前に自分の受ける級の検定料を確認しておいてください。漢検は級によって検定料が違います。
| 受検級 | 検定料 |
|---|---|
| 1級 | 6,000円 |
| 準1級 | 5,500円 |
| 2級 | 4,500円 |
| 準2~4級 | 各3,500円 |
| 5~7級 | 各3,000円 |
| 8~10級 | 各2,500円 |
ただし、団体受検(2~10級のみ実施)は個人受検より1000円安く、CBT受検はどの級も1000円安く受けることができます。
次に申し込み方法です。申し込み方法は以下の3種類があります。
- 個人受検
- CBT受検
- 団体受検
では、一つずつ申し込み方法を解説していきます。
個人受検の申請の手順
個人受検とは、年3回実施され、協会が全国主要都市に設けた公開会場で受検する方法です。
では個人受検の申請方法の手順を解説していきます。申し込みページからこの記事の手順に沿って申し込みを進めてみてください。
漢検公式の申し込みページはこちらから↓
個人受検の流れ | 個人受検 | 日本漢字能力検定 (kanken.or.jp)
1 受検者アカウントの作成
漢検を個人受検で申し込む際はネットで申し込みをします。その際に必要となるのが受検者アカウントというものです。アカウント登録の際は受験する本人の情報(氏名・生年月日)でご登録ください。
アカウントの登録はこちらからできます→日本漢字能力検定、文章読解・作成能力検定 My Page (ijuken.com)
なお、登録を完了したら、マイページへログインをしてください。そこから申し込みができるようになります。
2 申し込み情報(日程、受検級、受検地区)の入力
マイページの「申込」より、申し込み情報を入力します。情報入力の際に注意点がいくつかあるので紹介します。
1 日程
漢字検定は通常年3回行われており、6月・10月・2月ごろに試験があります。試験の実施日と自分の都合が合うかどうかをきちんと確かめてから日程を選択しましょう
2 受検級
漢字検定は様々なレベルの階級があります。無理をせずに自分と同じくらいのレベルの級から受けていきましょう。また、検定料も受験級によって値段が違うので注意が必要です。
3 受験検地区
漢検では受検地区も選択することができます。なるべく自分の住んでる場所と近い会場を選びましょう。また、「満席」と表示されている会場は申込人数が定員に達しているため、お申し込みができません。
3 支払い方法の選択
検定料の支払方法をクレジットカード、コンビニ/銀行ATM(Pay-easy)、QRコード決済(PayPay・LINEPay)のいずれかから選択します。
各支払方法で支払いを完了したら申し込み完了です!!
申し込みが完了したら検定日約1週間前に申し込み時に入力した住所に受検票が届くのでそれを検定日に持参して、試験に臨みましょう!!
CBT受検の申請の手順
CBT受検とは、コンピューターを使って漢検(2~7級)を受検するシステムです(※CBTとはComputer Based Testingの略)。CBT受検は年3回の検定日に限定されずに、都合のよい日程を選んで受検できるので、忙しい方にも受検できるように作られた受検方式です。
ではCBT受検の申請方法の手順を解説していきます。申し込みページからこの記事の手順に沿って申し込みを進めてみてください。
申し込みはこちらからできます→日本漢字能力検定(コンピューターテスト) | CBT-Solutions CBT/PBT試験 受験者ポータルサイト
1 受検者アカウントの作成
CBT受検も個人受検と同じように受検者アカウントの作成が必要です。
アカウントの登録はこちらからできます→日本漢字能力検定、文章読解・作成能力検定 My Page (ijuken.com)
なお、登録を完了したら、マイページへログインをしてください。そこから申し込みができるようになります。
2 申し込み情報(日程、受検級、受検地区)と支払い方法の入力
次に申し込み情報と支払い方法を入力します。
CBT受検は選べる日程が個人受検より多いのでかなり自由が利きます。
受検級、受検地区を選択したら次に支払い方法を選択します。
支払い方法は
・クレジットカード決済
・コンビニエンスストア/Pay-easy決済
(Pay-easy:ゆうちょ銀行ATM・ゆうちょダイレクト、銀行などのATMやネットバンキング)
・受検チケット事前購入(バウチャー対応)
とあるのでこの中からお選びください。
支払いが済むと、申し込みが完了です!
申し込みが完了すると、ご登録のEメールアドレスに予約完了のお知らせが来るはずなので、 お申込内容、お支払手続き及び試験会場地図を必ず確認してください。
団体受検の申請方法
団体受検とは学校や学習塾などで実施され、団体が選択した検定日に行われます。
団体受検志願者の方は団体の担当者に申し込みます。なので学校の先生や塾の先生などに手続きをしてもらってください。
まとめ
この記事では漢検の概要や各階級のレベル、申し込み方法について解説しました。
漢検は級の種類も多く、申請方法も多いのでややこしいと感じるかもしれません。
しかし漢検を取得しておくと、漢字読み書き力の向上にもなるし、漢字のスキルを持っているという証明にもなります。

漢字が苦手な人ほど試してほしい!この漢検のおかげで漢字嫌いを克服した人も多いよ!
また、このほかにも数検、英検などの資格情報を掲載しているので気になる方はそちらも見てください!