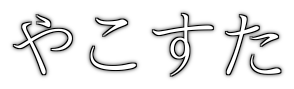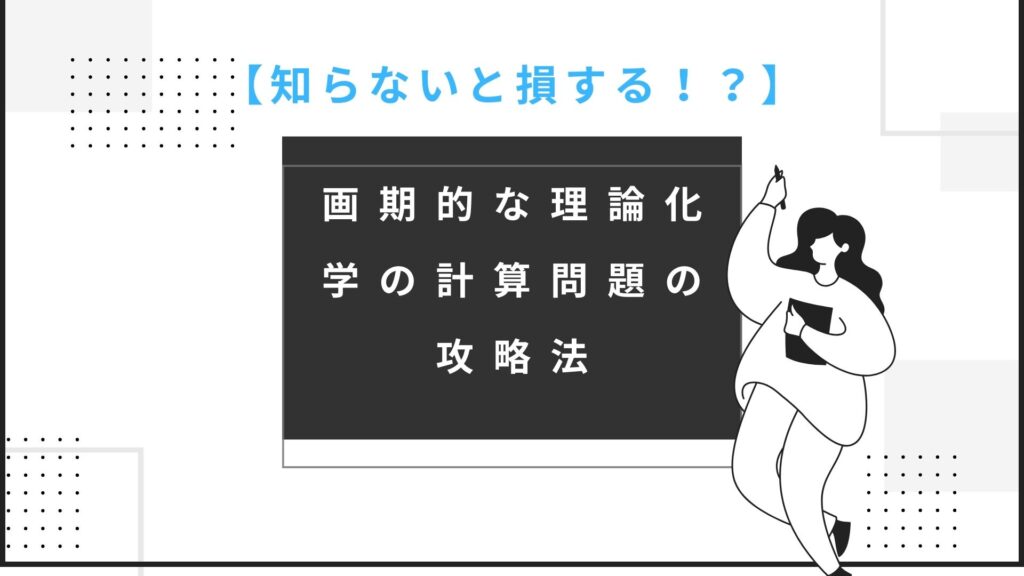
こんにちは!やこです。今回は画期的な理論化学の計算問題の攻略法を伝授していこうと思います。

化学の計算問題が苦手・・・
理論化学が苦手・・・
以上のような悩みをこの記事で解決します。
- 攻略法その1「理論化学の計算問題は分野によって解き方が違うことを知る」
- 攻略法その2「分野ごとの知識と解法を覚える」
- 攻略法その3「後は演習で慣れるのみ!!」
理論化学の計算問題は苦手な人がかなり多い印象があります。しかしちゃんとした「攻略法」で計算問題の演習を積めば確実に計算問題で点を取れるようになります。今回はその「攻略法」というのを詳しく解説していくのでぜひ最後までこの記事を読んで見てくださいね!
また化学の3分野(理論、有機、無機)のそれぞれの特徴について知りたい方はこちらの記事を参考にしてください!

では早速解説していきましょう!
攻略法その1「理論化学の計算問題は分野によって解き方が違うことを知る」

理論化学では化学基礎と化学に分けられており、化学基礎は文系理系問わず学習するいわば化学の超基本的な内容で、一方化学は理系のみが学習する少し発展的な内容となっています。
理論化学で習う分野は以下の通りになります。
| No | 分野名 | 学習内容 | 化学or化学基礎 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物質の構成粒子 | 原子構造など | 化学基礎 |
| 2 | 物質量と化学反応式 | mol計算や反応式の書き方など | 化学基礎 |
| 3 | 化学結合と結晶 | 結合と結晶の種類など | 化学基礎 |
| 4 | 物質の三体 気体の法則 | 物質の三体や状態方程式など | 化学基礎and化学 |
| 5 | 溶液 | 飽和水溶液やコロイドなど | 化学 |
| 6 | 化学反応とエネルギー | 熱計算など | 化学 |
| 7 | 反応の速さと平衡 | 反応速度式や化学平衡の法則など | 化学 |
| 8 | 酸と塩基 | 中和計算や電離など | 化学基礎and化学 |
| 9 | 酸化還元と電池 | 酸化還元反応や電池、電気分解など | 化学基礎and化学 |
このように理論化学には様々な分野に分けられていて、それぞれの分野に計算問題が存在します。

No5の溶液の分野だったらヘンリーの法則を使った気体の溶解度計算、No7の平衡の分野だったら電離平衡の計算や緩衝液など扱った計算など、分野ごとに様々な計算問題が存在するよ!!
そして、理論化学は分野ごとに学習する内容も全く違うので計算問題の解き方も分野ごとで全く違います。つまり理論化学の計算問題には分野ごとにそれぞれ独自の解き方があるのです。
まずは化学の計算は分野ごとに解き方が全く違うということだけを覚えておいてください。
このことを知っておくだけでかなり化学の計算問題の攻略に近づけます。
攻略法その2「分野ごとの知識と解法を覚える」
化学の計算は分野ごとに解き方が違うことを理解してもらった上で、次は実際に計算問題をどのような方法で攻略していくかを説明します。
わかりやすく説明するために一つの分野を例にして計算問題の攻略法を解説します。
今回は理論化学の中でも入試で頻出の分野「電気化学」を例にします。
まず電気化学の計算問題と言えばやはり酸化還元反応を利用した電極反応の物質計算問題が定番です。
では、実際にどのようにしてこの電気化学の計算問題を攻略していくのか?それは、
電気化学の知識と電気化学独自の計算の解法を覚える
ということだけをして攻略していきます。
これだけでは説明不足なので具体的に説明します。
まず電気化学の計算問題を解くには当然電気化学の知識(電極反応の種類や酸化還元の知識やファラデー定数についてなど)が必要です。
計算をするには知識が必要なのは当然なのでこれはわかりやすいと思います。
次に電気化学独自の計算の解法を覚えます。これが意外と知らない人が多いのではないでしょうか。
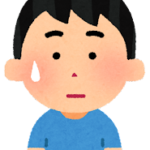
電気化学独自の計算の解法なんてほんとにあるの?
実はあるんです!!
電気化学には
Step1 電極の反応を明らかにして、流れる電子の物質量を求める
Step2 問題で与えられている物質の量を明らかにして問われている物質の量(解答)を文字にする。
Step3 Step1、Step2で手に入れた情報をもとに問われている物質の量を文字と置いた一次式の比例式を解いて計算の結果を問われている解答の形式で答える。
といった。電気化学独自の計算問題の解き方がきちんと存在します。
このように電気化学独自の知識と解き方さえ覚えてしまえば電気化学の計算問題をすらすら解くことができるようになるのです。
もちろんこれはあくまで「電気化学」の話ですが、他の分野にもそれぞれ独自の知識をと解法が存在します。
ですので分野ごとに「知識と解法」をしっかり覚えれば理論化学を簡単に攻略できてしまいます。
攻略法その3「後は演習で慣れるのみ!!」
攻略法2では分野ごとに「知識と解法」を覚えることについて解説しましたが、こんな風に思った方もいるかもしれません。

分野ごとの解法なんてどこで教わればいいの?
たしかに、実際に分野ごとに違う解き方をしっかり教えてもらえる機会はなかなか学校や塾でもないかもしれませんね。
そんな人にお勧めしたい参考書があります。その参考書は「照井式問題集 理論化学 計算問題の解き方」という本です!
この「照井式問題集 理論化学 計算問題の解き方」という参考書は攻略法2で説明した「分野ごとに知識と解法を覚える」という勉強法にぴったりな構成になっています。
また、この参考書は分野ごとに計算問題を攻略するために必要な知識と解法を詳しく説明してくれます。
さらに練習問題も豊富な数が掲載されているので計算問題に沢山触れることもできてかなりの実力が付くと思います。
解法と知識を覚えてしまえばあとはその解法と知識を正しく扱えるかどうかの演習をするだけです。
演習を積み重ね、正しい解法と知識をつければ化学の計算問題を確実に解けるようになっているでしょう。
その演習を行うためにもぜひ今回紹介した参考書「照井式問題集 理論化学 計算問題の解き方」を使ってみてください!
進路に迷っている高校生へ
将来の夢や目標が明確なら、行きたい大学も明確で迷いも少ないでしょう。
でも、多くの高校生が、「何に興味があるかわからない」「この大学を卒業したらどんな仕事に就くんだろう?」「自分に合った大学はどこだろう?」と悩みを抱えています。
そんな方はぜひ様々な大学や専門学校の資料やパンフレットに目を通しておくのをお勧めします!
パンフレットや入学案内には、以下のような情報が掲載されています。
- 大学の概要・理念
- 学部・学科のカリキュラム
- 入試情報
- 卒業後の進路
- キャンパス情報
- 学費・奨学金制度
- オープンキャンパス情報
これらの情報を読み込むことで、それぞれの学校の特色や強みを比較検討することができ、自分の興味がある学校が見つけられます。
また、オープンキャンパスに実際に足を運ぶ際の参考にしたり、志望校選びを絞り込む際の材料としても役立ちます。
ですのでぜひ自分の将来のためにも興味のある大学や専門学校のパンフレットを集めておきましょう!!
資料請求はぜひ「スタティサプリ」をご利用ください!「スタディサプリ」ではほぼすべての大学、専門学校のパンフレットを無料で取り寄せることができます。

直接大学などにいかなくても、ネットからパンフレットを無料で取り寄せられるのがスタサプの魅力だよ!!
また、現在(2024年4月時点)10校以上のパンフレットを取り寄せると高校生限定で図書カード1000円分を無料でもらえるのでぜひ資料請求をしてみてください!!
「スタサプ」の資料請求はこちらから!

図書カード1000円分なら参考書も一冊買えそうだよね!!
まとめ
今回は理論化学の計算問題の画期的な攻略法について解説しました。
いかがだったでしょうか?もし今回の記事が参考になっていただけたのであれば著者としてもとても嬉しいです!
また、有機化学や無機化学の勉強法についても知りたい方はこちらも参考にしてください。